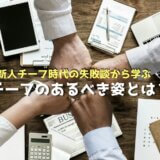当サイトでは、運営維持のために広告を使用しています。
スーパーマーケットでは季節イベントは売上を作る為の超重要機会です。
年間の販促と祭日などの一覧にしたカレンダーです (ougonnetlife.com)
そんな時に昨年の反省書は非常に重要な手掛かりとなりますが、そもそも「反省書の読み取り方がわからない」「計画の立て方がわからない」方もいるかと思います。
この記事ではスーパーマーケットで10年ほど働いた筆者が新人チーフに向けて、昨年の反省書の見方から歳時記の販売計画の仕方まで解説しようと思います。
具体的には
・前年の反省書の読み取り方
→どのデータをどういう風に見るのか
・それに対してどのような計画を立てていけばいいのか
・歳時記に準備すること
・来年の為にどのようなデータを残せばいいのか
と、読むだけですぐに使える内容となっているのでまずはご一読下さい。
目次
昨年と今年の世の中・店舗状況について把握する
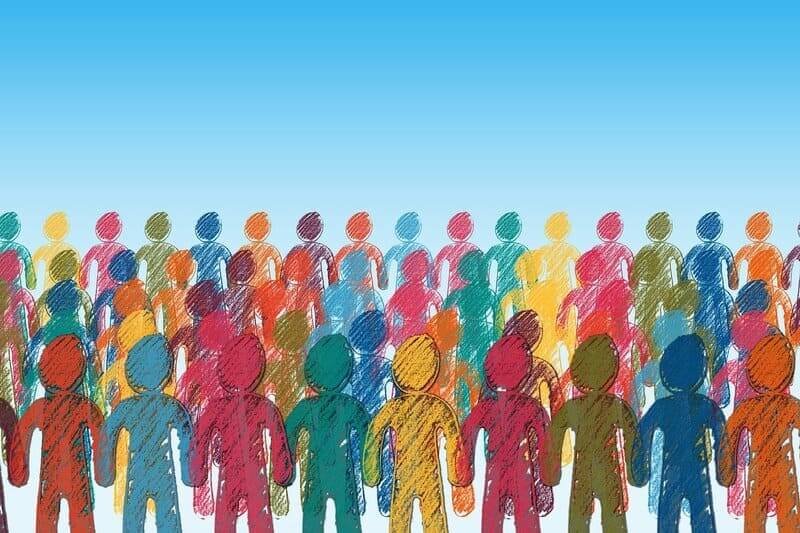
計画を立てる前に、昨年の世の中の人の動きや、売上の背景を知ることで、今年の売上を予測することに繋がります。
状況とは大きく3つあり、それぞれに細かい分類があります。
1.世の中の状況を把握する
例①
・コロナで規制がかかって県をまたぐ移動ができなかった。
・巣ごもり需要で買いだめが多かった
・遠方へ出かける人がいなかった
・外食をする人が減っていた。
などスーパーマーケットの需要が高まっていた背景があるのであれば、今年も同じような動きになるのか?
それとも今年はお出かけムードであるのか?といった人の動きを予想します。
売上が上がった背景を見て、今年はどの商品で補填するのか?どのような商品に需要がありそうなのかを考えます。
例②
・曜日回りやオリンピックがあって祝日がずれていた…等。
曜日回りは非常に重要です。
例えばクリスマスは、1番売れる24日よりも土曜日であった25日の方が売れるなど、日付よりも家族で過ごしやすい曜日まわりの方が有利にはたらくことがあります。
また、祝日だったり祝日がずれていた場合に、単純に数字だけを見て数量を増やしてしまうと全く売れずにロスに繋がってしまいます。
どうして昨年はこの日が売れてこの日は売れなかったのかを注意深く見る必要があります。
例③
・原材料高騰でメーカーの食品の値上げがあった。
メーカーの値段が軒並み上がったが、自社ブランドの製品はそれよりも安い為、今年はその商品で売上を作ることができそう等。
2.昨年の天気状況を把握する
日ごとに天気を確認していきましょう。
昨年が雨だったから売れなかったのか?雨でも売れているため、晴れていたらもっと売れたのではないか?
例
・普段よりも気温が高くて需要のある商品に差が付いた等
また、もっと細かく見ていくと天気のせいで午後の方が売れたなどが出てくると思います。
3.昨年の店舗状況を把握する
店舗状況は人や商品、売場についてです。
①人員状況
例
・昨年よりもロングパートさんが1名少ないであるとか、昨年は病気で欠員が出ていた為に思ったように売上が作れなかった等
今年は人数がいるのであれば更なる売上の期待ができるし、人員がいないのであれば応援体制を組んだり早出のお願いをしたり、簡単な製造の商品で逃げることを考えることができます。
②商品状況
例
・昨年はどんな商品をメインで売っていたのか?その商品はいくつ販売していて売価がいくらでどのくらいのロスが出たのか?等
③売場状況
例
・昨年はどの時間帯でどれくらいのピークがあったのか?
・何をどの場所で販売していたのか?
どのような売場であったのか写真が残っているとわかりやすいです。
その時の写真を見てPOPの訴求がわかりにくい場合や訴求が弱いと感じたら強化します。
以上を踏まえた上でざっくりと状況把握をしていきます。
昨年の数値から売上の仮説を立てる

例えばの数値を用いて説明します。
先ほどの状況確認を踏まえて自部門の売上を見ていきましょう。
大事なのはその売上の数値は低いのか?高いのか?どうしてその数値になってしまったのか?を自分の中で仮説を立てていくことです。
この仮説を今年の製造に活かし、それが合っていたのか?間違っていたのかは当日修正しながら来年に活かしていくこととなります。
| 天気 | 雨 | はれ | はれ | はれ | あめ | はれ | はれ |
| カレンダー | 振替休日 | 盆の入り | |||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日付 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 |
| 売上(千円) | 130 | 125 | 120 | 120 | 150 | 190 | 160 |
| 昨年同日売上 | 158 | 140 | 123 | 125 | 160 | 150 | 180 |
| 同日昨対 | 82.3% | 89.3% | 97.6% | 96% | 93.8% | 127% | 88.9% |
| 値引きロス(千円) | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 廃棄ロス(千円) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| ロス率 | 9.2% | 3.2% | 5% | 5% | 0.7% | 1.58% | 4.4% |
例:月曜日なのに売上が高い
→昨年は振替休日になっている
→でも天気は雨
→廃棄ロスは2千円だけど、値引きロスが10千円もある!
きっと雨で客数が減った為に商品が売れなくて値引きでなんとかしたんだろうなぁ。
今年は晴れだから計画数量を増やしてみよう!
例:火曜日は水、木と比べて売上が5千円高い
→前日の雨で来れなかったお客さんが火曜日にスライドしたのかもしれない。
ということは同じように商品を増やしてしまったらロスになってしまう可能性もあるなぁ。
予想外に売れてしまっているから当日の値引きロスは1千円で廃棄ロスも3千円でこの時は商品が足りなかったんだろうなぁ。
例:金曜日は盆の入りで他の平日と比べるとぐんと売上が上がっている
→雨の日にも関わらず150千円の売上。値引きロスも1千円で廃棄ロスがないところを見ると商品が全然足りてないんだな。盆の入りはお客さんが多く来るなら今年はここを更に製造を強化して売上を取りに行こう!
あくまでも例になりますが、このように数字を見ることでどのような状況であったのか?
それを踏まえて今年はどうしたら良いのか仮説を立てることができます。
何も考えずに単純に昨年よりも数を増やすだけにしてしまうと
・天気の兼ね合い
・ロスの中身
上記を無視した根拠のない販売計画となり、信憑性に欠けたものとなってしまい、大きなロスや欠品の原因となります。
特に数値を見る際に、ロスの中身は非常に重要で値引きロスが多いのか?廃棄ロスが多いのか?で考えられる答えが変わります。
反省書に書き込むロスは「値引きロス+廃棄ロス」のロス率のみを書くのでなく、分けて書く必要があります。
曜日回りや天気を含めて売上の増やすところ、抑えるところの仮説を立てて1日あたりの目安を立てたら次はもっと細かく数字を見ていきます。
今年の本部政策を交えた売場レイアウトを作成する
本格的に数値を出して製造計画を作成する前に行いたいのが、売場レイアウトを先に作ることです。
今年はどのような政策でいくのか?本部はどのようなアイテムで売上や利益を取りに行こうとしているのか?
政策をチェックし、1番良い場所で何を展開していくのか計画を立てていきましょう。
売上を取りに行くアイテムと(だいたい低値入)とそれを補填する値入がいい利益を取りにいくアイテムの組み合わせが大切です。
昨年のデータを元に単品の計画を立てる
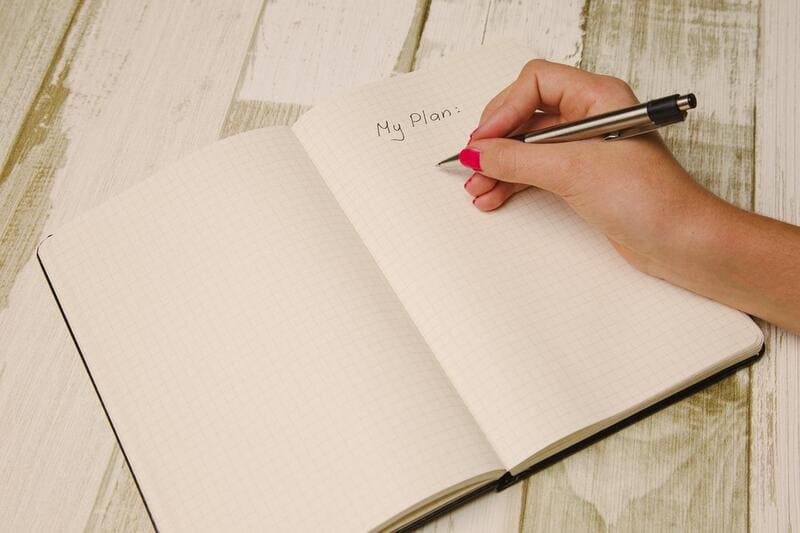
売場のイメージができたら、いよいよ細かい単品アイテムをどのくらい売るの計画していきます。
他社のスーパーのシステムはわかりませんが、単品データを拾うことができるツールがあるはずですので、先ほどの表であるならば祝日と盆の入りは特に何が売れたのか単品のデータを拾ってみましょう。
拾うのは単日のベスト20アイテムで良いと思います。
拾う項目は
・売価金額
・販売数量
・最終販売時刻
・値引き金額
・値引き数量
・ロス率
です。
なぜこの項目を拾うのかについて▼
100コ売れていて廃棄が0でも、その商品に値引きロスが多いのであれば無理して値引きで売っていたことになります。
また、値引き数量が多くても、最終販売時刻が13時であればそれでは数量が足りなすぎます。
数値を拾うことで、自分なりに今年は数量を増やしてみようなどの仮説を立てて計画します。
また、単品で昨年何が売れたのかがわからず、単日の売上ベースのみを適当な商品で増やしてしまうと、お客さんの需要を無視しているので売上をつくることができません。
売上の中身はどのような商品だったのかを確認し、最終販売時刻やロスからその商品が多かったのか?少なかったのか?を考えましょう。
また、商品は時間によっても需要が変わってきます。
例えばベーカリー部門は特にお昼需要が強いです。
普段は11~12時にピークがくるけど、13時が1番のピークだったなど、ピークがずれているか確認できるのであれば参考にしましょう。
1日の中で売れる商品をその時間帯に目一杯売るオペレーションを組むことで、昨年よりも売上UPが期待できます。
歳時記に準備すること
販売計画以外にも準備があるので紹介していきます。
予約商品の訴求物を用意する
各部門、予約物があると思うので、1ヶ月~2週間前には店内放送やPOPで予約物の告知をしましょう。
予約承り中の大きなPOPやボードを設置するのと、お客さんがもって帰れるチラシを置いておくと良いかと思います。
→予約が入ればデリカや水産の寿司は単価が高いので売上UPが期待できます。
・商品の写真はおいしそうに見えるものを使用
・ボードの字は誰が見ても遠くからでも見えるくらい大きいな文字で作成
・店内放送を1日2回ほど行って予約訴求を行う
商品の種類や価格帯、どこで予約ができるのかの案内する
送り込み商品や発注の確認
会社によって祝日はお休みで発注に変動がある場合もあるので注意が必要です。
また、送り込み数量は確認し、自分の発注に無駄がないようにしましょう。
特に普段よりも販売数量が増えるので、製造部門は包材の数に気を付けましょう!!
商品POPの作成
昨年のPOPが訴求が弱いなら訴求を強めにします。
お買い得感が上がる文言や文字を大きくするなど工夫すると良いかと思います。
スーパーマーケットで「売る」為の販促POPの作り方と心構え
歳時記の計画をパートさんへの落とし込み
計画は社員だけチーフだけで計画を完結するのではなく、
何日のメインの売り込みは何なのか?
その商品はどこでどれだけやるのか?
手土産商品はいつどこでやるのか?
その他気を付けることは何があるのか?
など、ざっくりとでも良いのでパートさんに計画の落とし込みをしましょう。
また、その話をした上で当日のオペレーションの変更や良い案があれば取り入れて、作業をしやすいようにしておくとよいです。
パートさんに話すことで、作業効率が上がり目標達成に繋がります。
来年の為にどのようなことを反省書へ残せばいいのか?
1年前のことなんて当然記憶にないしスーパーは異動も多いため、同じ担当者が今年もまたその店を担当しているとは限りません。
自分でない人物が読んでも理解できるように書くことが大切です。
各社でフォーマットはあるかと思いますが
・世の中の状況的なもの(コロナ特需アリ等)
・部門状況→人数、オペレーション(どのように回したか)
・ロスがロス率のみになっている場合は値引きロス金額、廃棄ロス金額の記載
・天気
・特に動きが変則的だった日の記載→ピークの時間帯売上(例えば13~14時で30千円など)
売れた商品が〇〇なら、曜日も加味して来年は▼▼売りましょうと数量まで書いておくと来年が楽です
その他気になったことは記載。
1日1枚A4 用紙を用意しておいて気になったことを記載しておくとモレがありません。
まとめ
以上がスーパーマーケットにおける販売計画の立て方となります。
昨年の状況、今年の状況を比べることから始めて、昨年の数値でわかることから仮説を立てて今年の販売計画を立てていきます。
正直失敗かどうかは当日やってみるまでわかりません。
まずは数値を読みとり…ということをやってみることがはじまりとなります。
もしかしたら計画以上に売れてしまうかもしれませんが、その都度修正してその時困ったことを反省書に書いて翌年に活かしていきましょう。